剽窃禁止(FPRn8712546-1)
《おうとうしゃ カレントコラム アーカイブ》
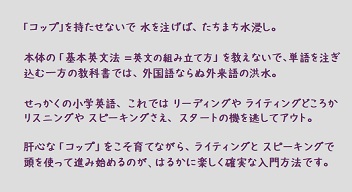
◎ 上の写真は、桜冬舎 2021年6月の広告切抜き。
以前、このカレントコラムの3ページ目「思考言語への第一歩」(特にその下欄の注)で小学英語の懸念を書いておいたが、やはりそんな気配だ。現場の声はともかく「早期教育が大事」という触れ込みで始まった訳だが、その「外国語の早期教育」は教科書では 一体どこから始まっているのだろう。
言うまでもなく言語は叙述、すなわち 文 だ。「文の組み立て方」を第一歩から学ばせて、その上に単語をどんどん乗せて行けば いくらでも楽しく実質的な 外国語 の勉強ができる。 逆に ゆとり教育の伝統で「文の組み立て方」を避け、英単語でお茶を濁していたのでは、それらはいつまでたっても「外来語」。外国語ではなく日本語の領域だ。
「英語の先進教育」などと 浮かれていればいるほど、そして日々の授業場面では 例えばゲーム感覚等で英単語を扱い 盛りあげてしまうほど、やがて肝心の「文」の勉強が始まる頃には 子供たちは知性が麻痺して眠くなってしまう。 それでも企画した側から見れば、英単語を詰め込めば 消費者英語(=植民地英語)として大成功 ということにもなるらしいから 深層は怖い。
子供にとっては貴重な貴重な入門期。自分の状況を選ぶことができないのだから、要は 教える側が 周りの風潮に流されず、外国語の本体(文の組み立て方)を考えさせながら、手を抜かず易しく教え続けること。
それにしても 日本では「英語検定」がほぼ《義務》だが、逆に英米で「日本語検定」が要求されるなどということがあり得るだろうか?
単純に「これからは英語の時代だ」と 浮かれていると、かつて「これからは日本語の時代だ」と氏名まで変えさせられた彼(か)の国の人びとと同じ悲劇のパターンさえちらつく。
と そこまでは言わないにしても、《義務教育》に「イギリス・アメリカ語」が組み込まれているということは、取りも直さず「イギリス・アメリカ語」の修得が 日本人にとって ほぼ《義務》だというところまで来ているということではないのか。実際問題として、ここまで「外国語の早期教育」が重視されながら、なぜ「イギリス・アメリカ語」以外の外国語の自由な選択が考慮される方向に進んで行かないのか。
日頃、労働法制や軍事法制が変えられると ある程度 世の中は騒がしくなるが、もっと根本的な教育行政の方針が変わっても、「変える目的は何なのだろう」と気づき 考える人はまず居ない・・・・。 それどころか 教育関係者・被教育関係者を問わず大方は《現実論者》だから、教科書が改訂される度に 不安な《現実》の中をオロオロとつき従い、そこを商機に 教育産業が漁(すな)どり回ることになる。
といった憎まれ口は、後日 新教科書をまとめて検討する時まで慎むことにしよう。今回の改定には なかなか面白い面もあることだし・・・・