剽窃禁止(FPRn8712546-1)
《おうとうしゃの本棚から アーカイブ》
「石切り山の人びと」 偕成社
桜冬舎の本棚から 8
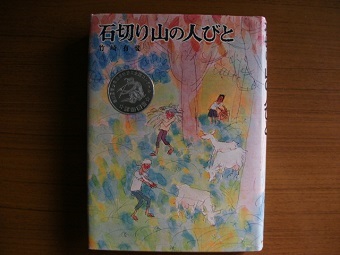
竹崎有斐 著、北島新平 絵、「石切り山の人びと」 偕成社
まず、出版社の紹介文を引用。
《 権六たちの悪童が支配してきた座敷山に、持ち主だと名のる田子老人一家が越してきて対立した。いっぽう、権六のおとうは、権力に石まぶの仕事場をうばわれようとし、必死に抵抗していた。戦時下の熊本を舞台に展開する激動の人間模様。》
「野うさぎ村の戦争」(植松要作 著)と並ぶ、「桜冬舎の本棚」 きっての名作。
これが子供向けの本なのかと驚く中身の濃さだが、それでいて紛れもなく 痛快な児童書。
この欄で推奨してきた本とは違って、初めから終わりまでストーリーにぐいぐい引き込むタイプ。大人の筋と子供の筋とが組み合いながら どちらも骨太に進んでゆく。そして後半から終盤へと進むほど ますます中身が濃くなり、背後の状況や意味を探して 「立ち止まり 立ち止まりして」読んで行く 読書になるので 読み応えも十分。その迫力も凄い。
「小学高学年から」となっているが、子供に目隠しをするような甘さは一切ない。戦時下の権力への抵抗と、やがて社会の崩壊に向かう 大人でも改めて胸を突かれる現実にまで、避けることなく 前半の痛快さの延長で連れて行ってくれる。合間に現れる重みのある分析も見事。今の児童書の範疇ではとらえきれない 貴重で真剣な読書体験になること必至だ。
鍵になるのは、単に「都会化が進んでいない時代」ということではない。以前から、「生活が生産の場から離れていない内容の本を・・・」と奨めてきたが、この本は その生産の場そのものが大きなスケールで描かれている。その生産手段が ことごとく権力に呑み込まれ破壊されて行く 悲しい歴史の現実が 子供にもありありと理解できる。そして上り詰めた最後、たった三行の短い段落が 万感胸に迫る。
そしてもう一つ。子供をここまで連れてゆけるのは、まさに母語の力。施 光恒さんが「英語化は愚民化」と言ったのは まさにこの現実なのだろう。(カレントコラム、「思考言語への第一歩」の下注を参照)
最後に 大石真氏の解説文から引用。
《私は、この作品を読みおえて、中学1年で読んだ「子供の四季」の感激を思いだしました。それは、それまでに読んだ童話や、少年小説から受けた感動とは、まったくちがった感動でした。そして、私の関心はおとなの小説へと移っていったのですが、「石切り山の人びと」も現代の少年少女にとって、おとなと子供の世界を結ぶかけ橋のような作品に思えてなりません。》